フィリップ・デルヴス・ブロートン さんの著作を、
【サラリーマンYouTuber】のサラタメさんが解説している動画を紹介したいと思います。
題名から見ると、営業不要論のようにも見えますが
実際はその真逆で、営業こそが世界一やりがいのある仕事だという話
原題は「The Art of The Sale」となっているので
日本語で出版する時、ひねった題名にしたということでしょう。
【拒絶】
サラタメさんによると
この本のポイントは「拒絶」
拒絶と言うと、ネガティブイメージを持たれる方も多いと思いますが
実際には、多く「NO」と言われた人ほど、営業成績が良いそうです。
つまり拒絶をポジティブに捉えているわけです。本の副題も
【営業は、拒絶から始まる世界一やりがいのある仕事】
となっています。
では何故
多く「NO」と言われた人ほど、営業成績が良いのかと言えば
それだけ多くの人にアプローチしているからであり
「NO」と言われるまで提案し続けるからだという事です
例えば、一つ商品が売れたら
そこで終わるのではなく
次々と他の商品も提案していくという事です
そうするといつかは
相手が「もう結構」となるので
「NO」と言われるまで、営業するといことは
相手の必要を全て満たすまで営業した結果というわけです
また少し面白いのは
営業活動の例としてキリスト教の布教活動
やアップルストアを例にあげている点です
キリスト教のことを
最も古く、最も大きく、巧みな営業であると称しています
【使命感】
例えば免罪符は誤ったものとして認識されているが
それを売っていた司祭たちは、真面目に人を救いたいという使命感から売ったのだし
マッキントッシュのセールスマンに関しては
営業技術がある人を選ばずに、アップル製品のファンを販売員として雇った
だから、これらを売った人たちは
使命感を持って「これ本当に良いもので、あなたに必要だから買ってください」
と真心から言えたということです
反対に、自分は良いとも思っていないものを
会社に言われて営業している人達は
人の拒絶を、自分が拒絶されていると感じてメンタルをやられやすいとのことです
だから営業職につく人たちは
条件や待遇で会社を決めるのではなくて
自分が本当に好きな商品を
作っている会社に入り
それを全力で売るというのが
会社にとっても、その人にとっても、顧客にとっても幸せなのかも知れません
【所感】
当時(中世)のキリスト教がマイナーで
拒絶をされながら
何とか免罪符を売っていったというのは、ちょっと違っていて
当時のカトリック教会は、王様と権力を二分するほど
メジャーな存在でした
ただ初期キリスト教が
超マイナーな集団であり
初代の使徒達が「使命感」を持ってキリスト教を伝えたと言い換えれば
その通りです
それは聖書の使徒行伝という所を読めば分かります
コメント
この記事へのトラックバックはありません。





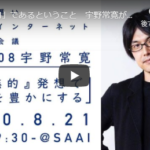









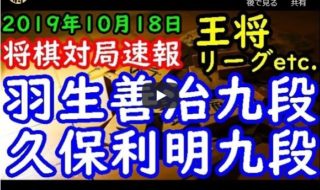
この記事へのコメントはありません。